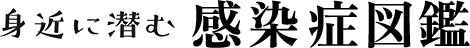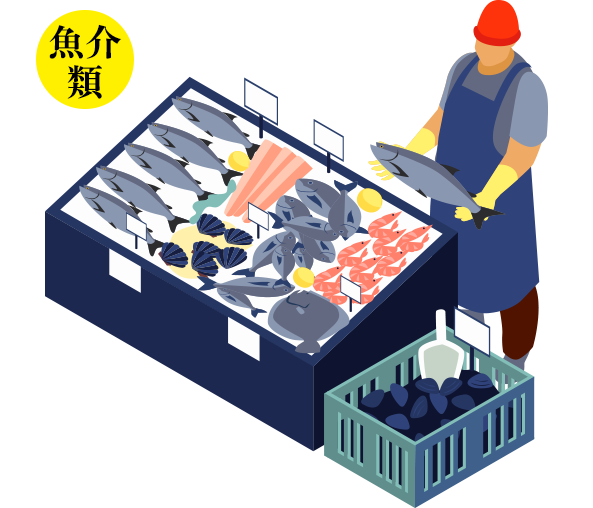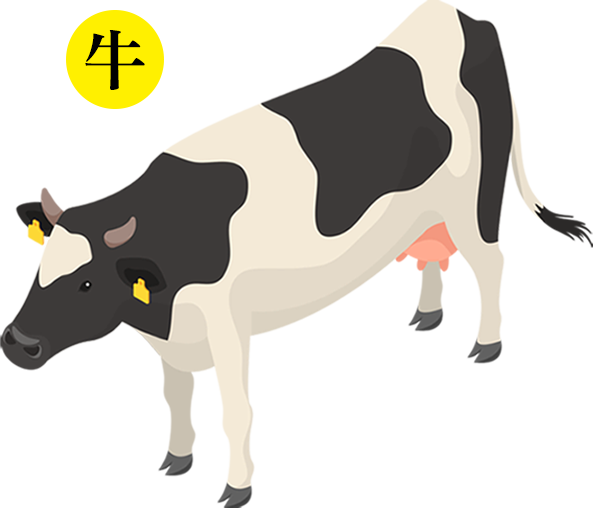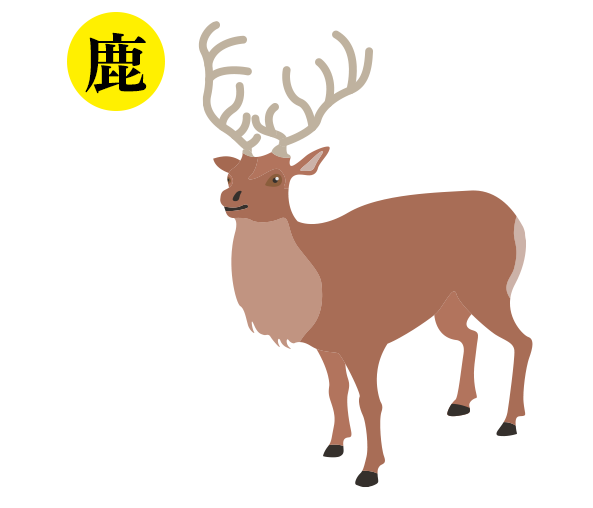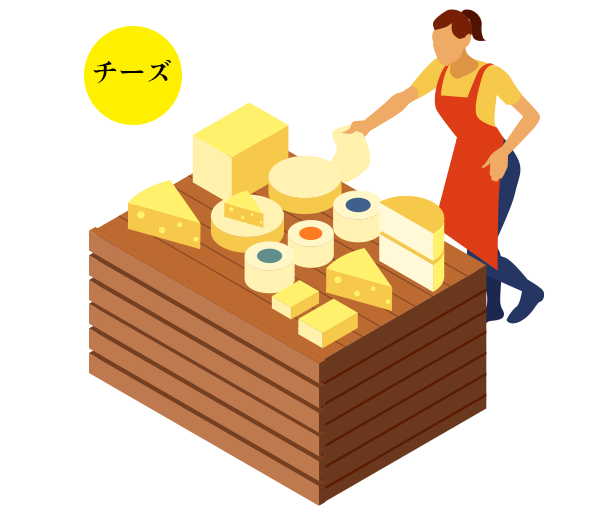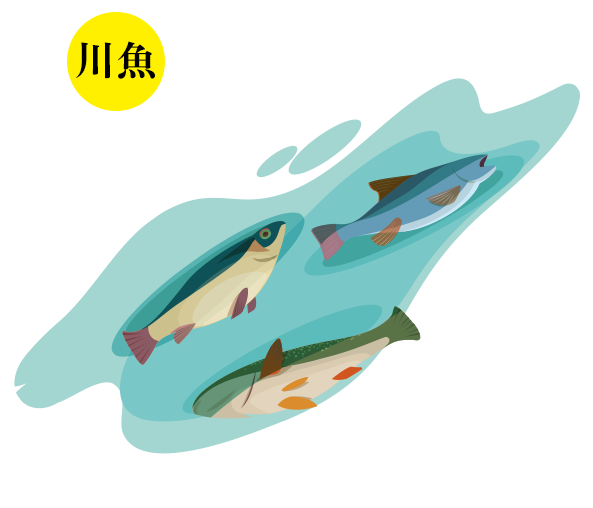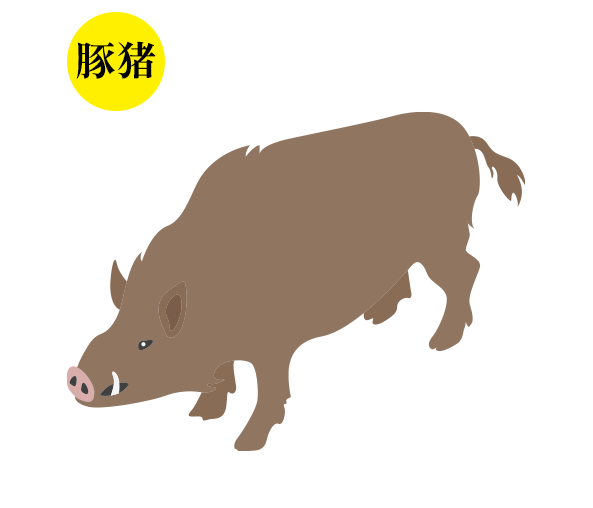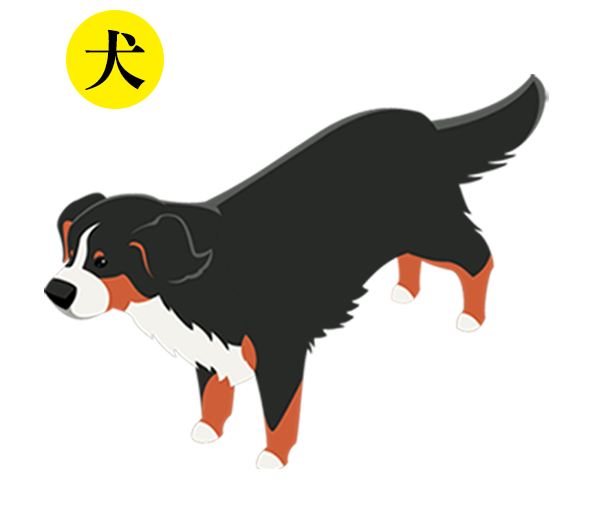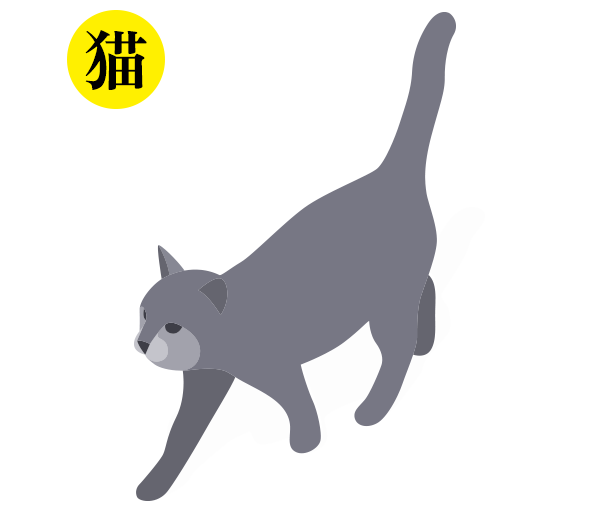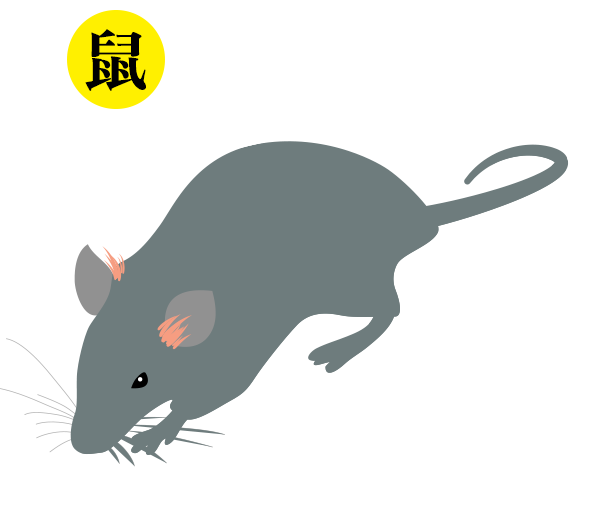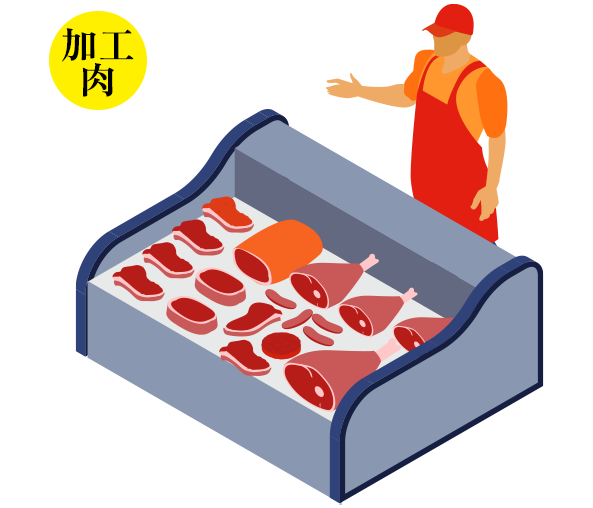Vibrio vulnificus感染症| Vibrio vulnificus Infection
感染経路と予防
Vibrio vulnificusは正常海洋微生物叢の一部である。1%程度の塩分濃度でも発育するため、河口域で海水(塩分濃度は約3.5%)と真水が交わる汽水域に生存している。また、海水温度が20℃を超えると検出される傾向がみられる。ヒトへの感染経路には生や加熱の不十分なカキなどの海産物の摂取による経口感染と、傷から感染する経皮感染がある。
院内では標準予防策を行う。予防として肝硬変患者などの高リスク患者では生カキなどの魚介類を避けることが推奨されている。また、皮膚に傷がある場合は海水暴露を避けることも重要である。
病態
V. vulnificusは病原性好塩性(2~4%程度の食塩要求) グラム陰性桿菌である。生や加熱の不十分なカキ、海産物を摂取することで水様性下痢を起こすことがある。また、肝疾患患者では経口摂取から菌血症、壊死性軟部組織感染症をきたす。
急激発症の悪寒戦慄、発熱を認め36時間以内に皮膚病変が出現してくる。皮膚に傷があるヒトが温かい海水に暴露し経皮感染を起こすこともある。急速に進行する蜂窩織炎、潰瘍形成を惹き起こし菌血症も合併することが多い。
診断・治療
血液培養や創部培養でV. vulnificusを分離することで診断する。蜂窩織炎は急速に進行する可能性があるため早期の抗菌薬投与が重要である。
フルオロキノロン、第3世代セフェム系抗菌薬、ドキシサイクリンは感性であることが多い。壊死性軟部組織感染症の場合はデブリドマンが必要で、状況によっては救命に患肢の切断が必要なこともある。そして、壊死性軟部組織感染症の場合は第3世代セフェム系抗菌薬にミノサイクリンまたはシプロフロキサシンで治療を行う。
出典
厚生労働省. [Internet]. May 31, 2006 [cited March 22, 2023]. Available from:
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/qa/060531-1.html#2
日本感染症学会. [Internet]. [cited March 22, 2023]. Available from:
https://www.kansensho.or.jp/ref/d61.html
Centers for Disease Control and Prevention. [Internet]. [updated 2022 Oct 17; cited 2023 Mar 22]. Available from:
https://www.cdc.gov/vibrio/wounds.html
このサイトの執筆者一覧
植田 秀樹,大川 直紀,大塚 喜人,窪田 佳史,倉澤 勘太,津山 頌章,中尾 仁彦,藤井 元輝,松田 直也