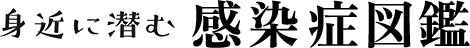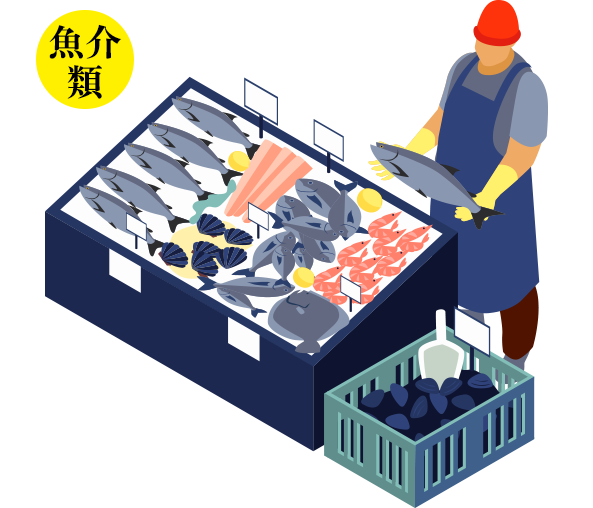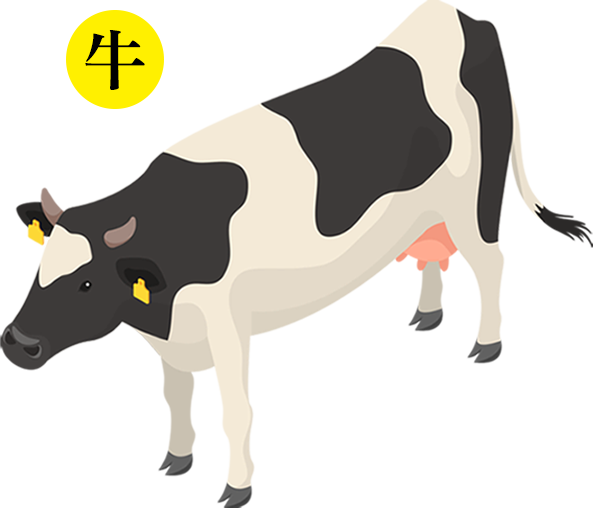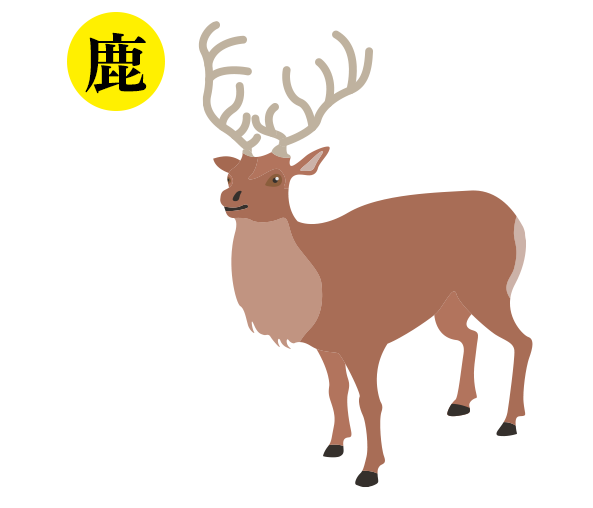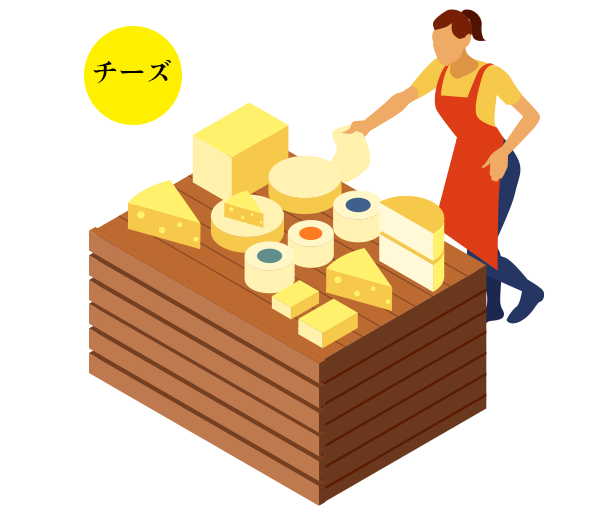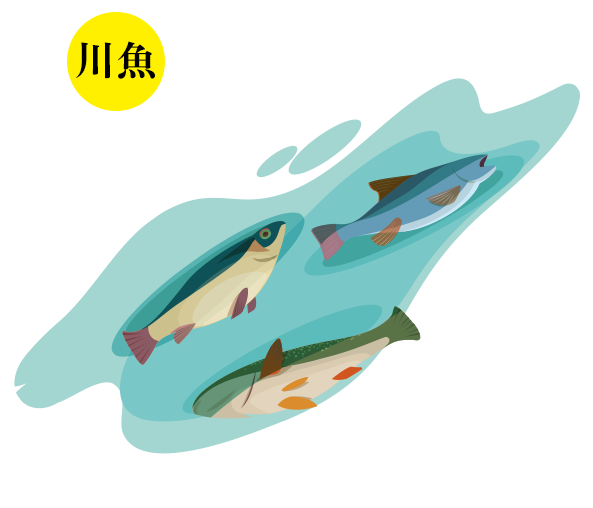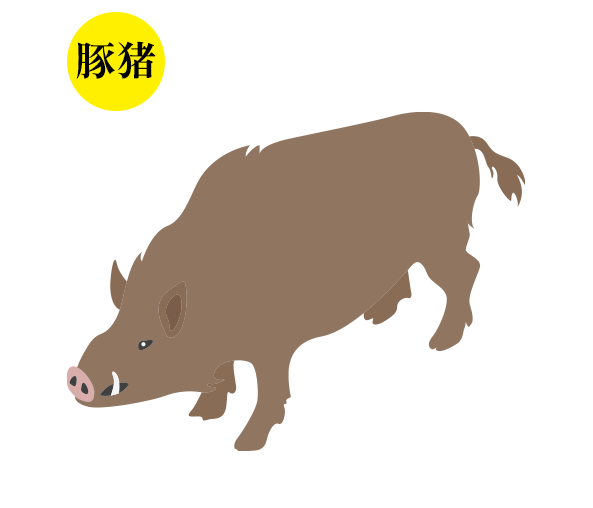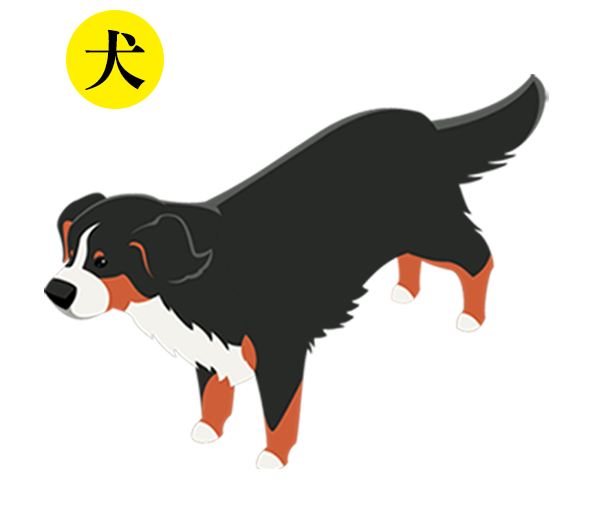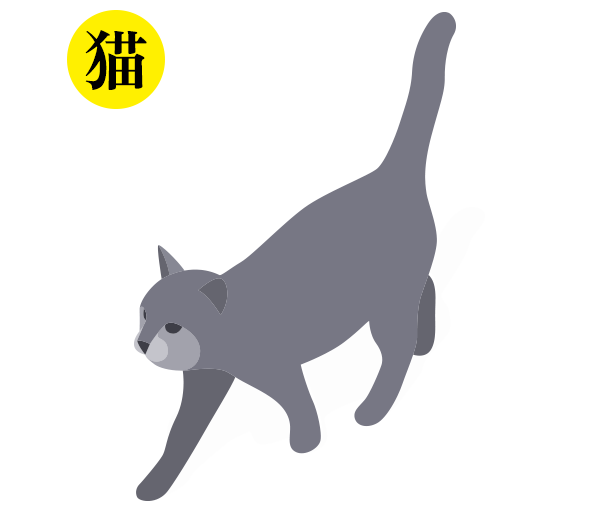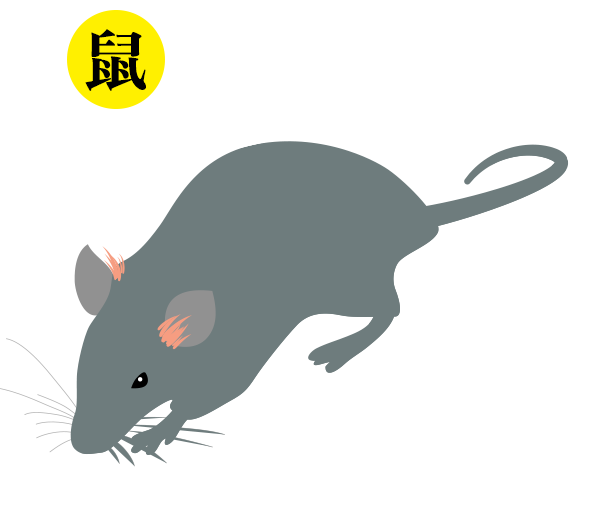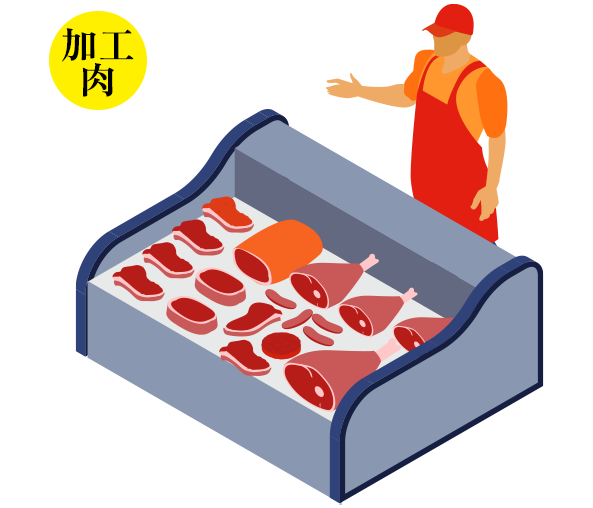日本海裂頭条虫症| Dibothriocephalus nihonkaiensis infection
感染経路と予防
日本海裂頭条虫はヒト、イヌ、クマなどを終宿主とする。成虫は数百万個の虫卵を生み糞便中に排泄される。虫卵は第一中間宿主のケンミジンコなどの甲殻類に摂取されるとその体内で幼虫になる。その後ケンミジンコがサクラマスやカラフトマスに摂取されると、ケンミジンコ内の幼虫はサクラマスなどの筋肉内でプレロセルコイドに発育する。
日本海裂頭条虫のプレロセルコイドに感染しているサクラマスやカラフトマスをヒトが生で摂食するか、または加熱不十分な状態で摂食することによって感染する。
サクラマスなどの生食を控えることが予防のために重要である。また、アメリカ食品医薬品局(FDA)はこれらの食材に対して内部温度63℃以上の調理または−20℃以下で24時間以上の凍結を推奨している。
病態
日本海裂頭条虫はヒトの小腸内で成虫となる。2~3週間の潜伏期を経て, 排便時に長い「きしめん様」の虫体が肛門から下垂することで感染に気づくことが多く、成虫はときに10mを超えることがある。
無症候性、または軽度の下痢や腹痛などを起こし、ときにビタミンB12欠乏症となることもある。
診断・治療
診断は肛門から排泄される片節や片節連鎖を確認して診断する。一般的にいわゆるテープ状に長く排出されるものは本種が多い。
近年、遺伝子検査を行い確定診断を行う症例が増えている。便の虫卵検査でも感染の有無がわかるが虫種は特定できない。
治療は抗寄生虫薬のプラジカンテルと下剤を使用する。頭節が残存していると再発するため便への排泄の確認が重要である。
出典
国立感染症研究所[Internet]. [updated 2019; cited 2023 Mar 22]. Available from:
https://www.niid.go.jp/niid/ja/route/parasite/1966-idsc/iasr-in/1809-kj3866.html
国立感染症研究所[Internet]. [updated 2018; cited 2023 Mar 22]. Available from:
https://idsc.niid.go.jp/iasr/CD-ROM/records/14/16106.htm
大阪府立環境科学研究所[Internet]. 2022 Apr 22 [cited 2023 Mar 22]. Available from:
http://www.iph.osaka.jp/s007/1000/2022_04/20220422135918.html
Centers for Disease Control and Prevention. [Internet]. [updated 2021 Jan 14; cited 2023 Mar 22]. Available from:
https://www.cdc.gov/parasites/diphyllobothrium/faqs.html
このサイトの執筆者一覧
植田 秀樹,大川 直紀,大塚 喜人,窪田 佳史,倉澤 勘太,津山 頌章,中尾 仁彦,藤井 元輝,松田 直也