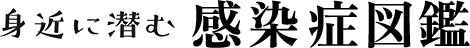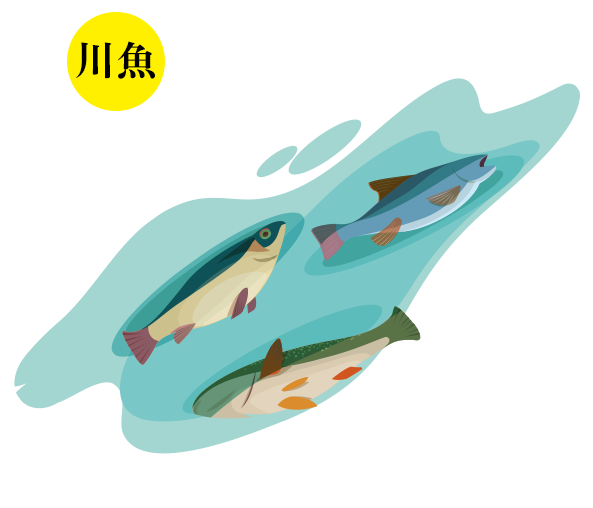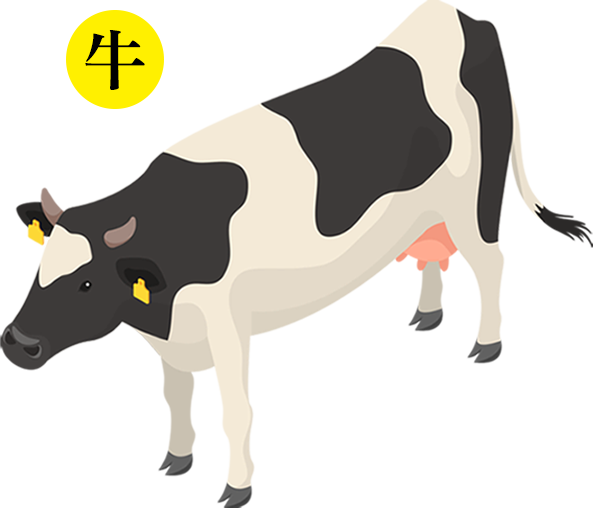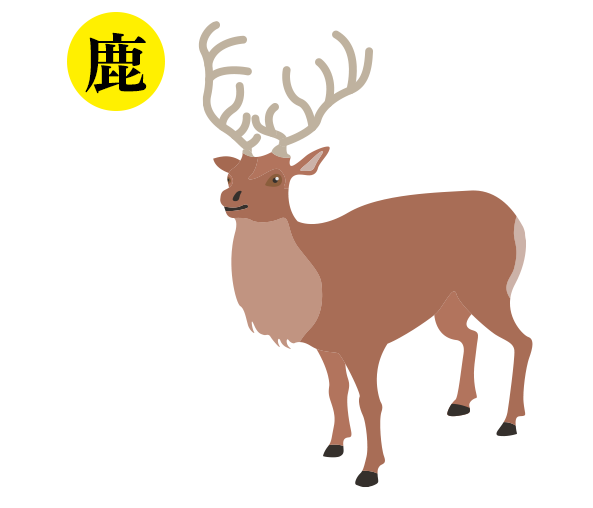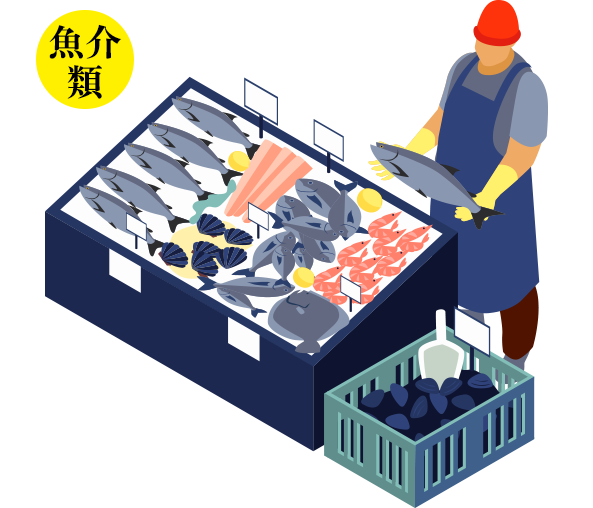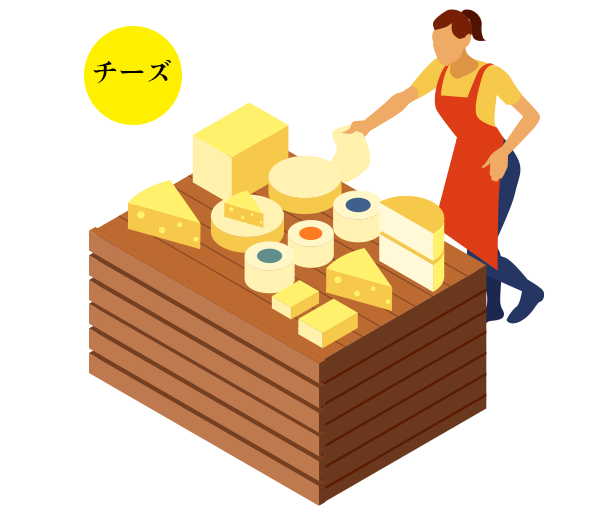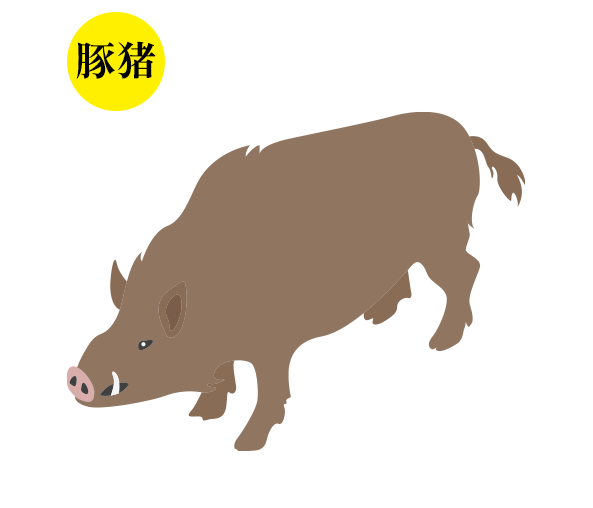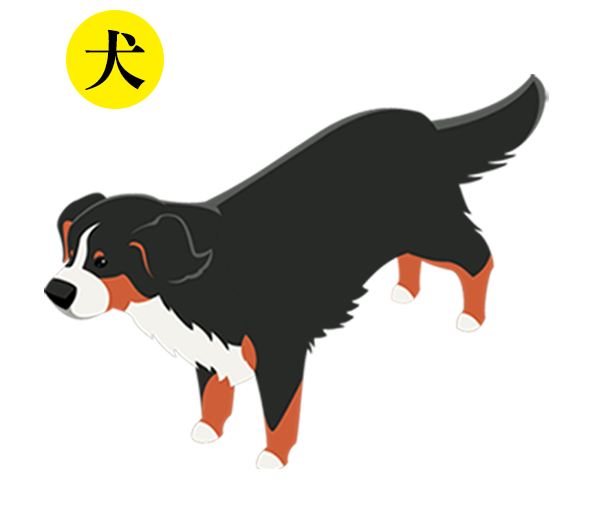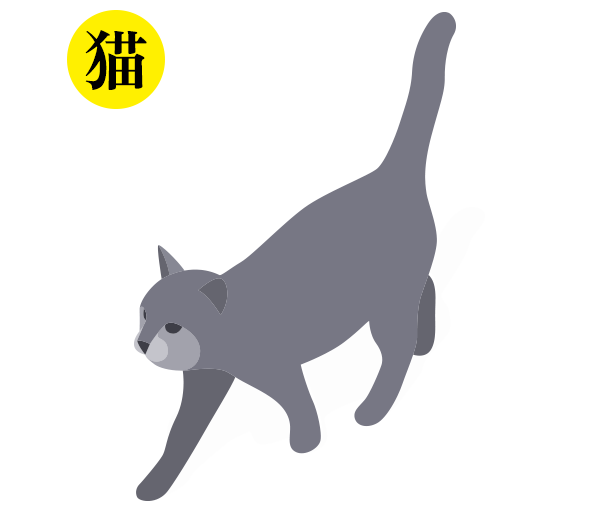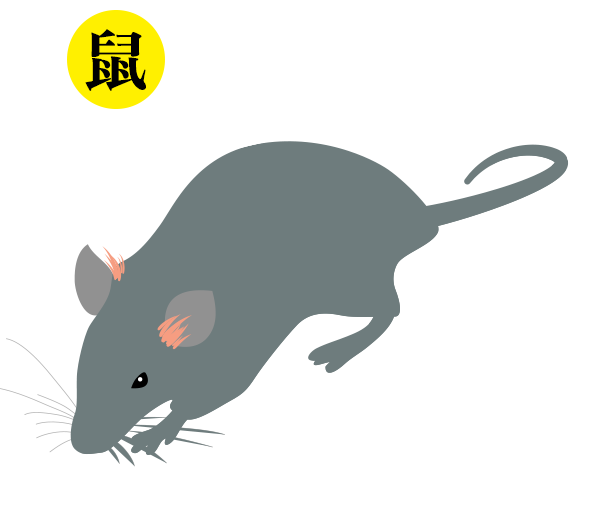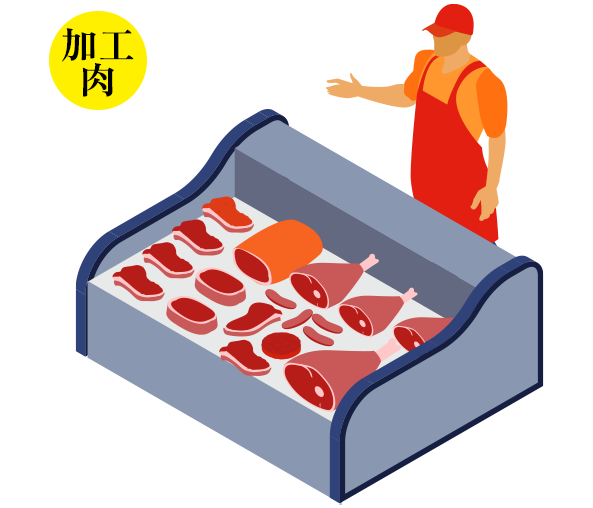顎口虫症 | Gnathostomiasis
感染経路と予防
国内で感染のリスクがあるのは、ドロレス顎口虫と日本顎口虫である。
顎口虫が寄生しているドジョウやヤマメ等の小型の淡水魚を生食すると、ヒトに感染する。淡水魚の生食をしないことが予防になる。
病態
ヒトは顎口虫の終宿主とはならない。幼虫は小腸を破った後で体内の様々な部位を迷走する。
皮下の浅いところを移動すると皮膚に移動性の爬行疹、紅斑、結節が現れる皮膚幼虫移行症を起こす。多くで末梢血の好酸球増多がみられる。
診断・治療
皮膚生検し、顎口虫を確認することで診断する。血清抗体の検出も有用である。
大部分は2〜3月以内に自然治癒すると考えられている。治療は虫体の摘出か、抗寄生虫薬であるアベンダゾールやイベルメクチンを内服する。
出典
好酸球増多を主症状とする寄生虫感染症 トキソカラ症,顎口虫症, 旋毛虫症. 臨床と微生物 41巻4号
J Travel Med . 2015 Sep-Oct;22(5):318-24.このサイトの執筆者一覧
植田 秀樹,大川 直紀,大塚 喜人,窪田 佳史,倉澤 勘太,津山 頌章,中尾 仁彦,藤井 元輝,松田 直也