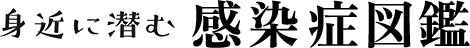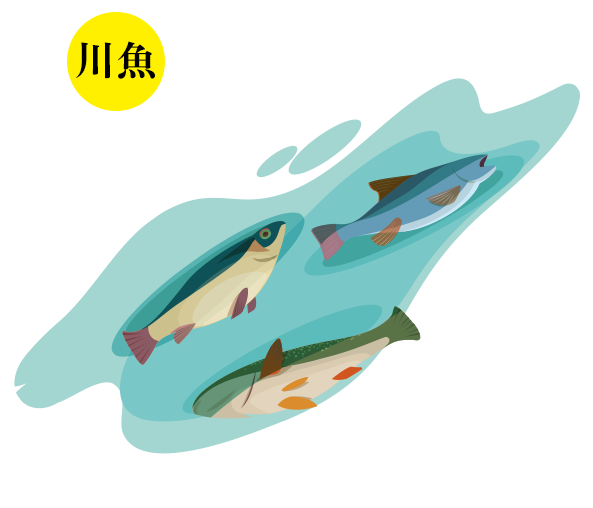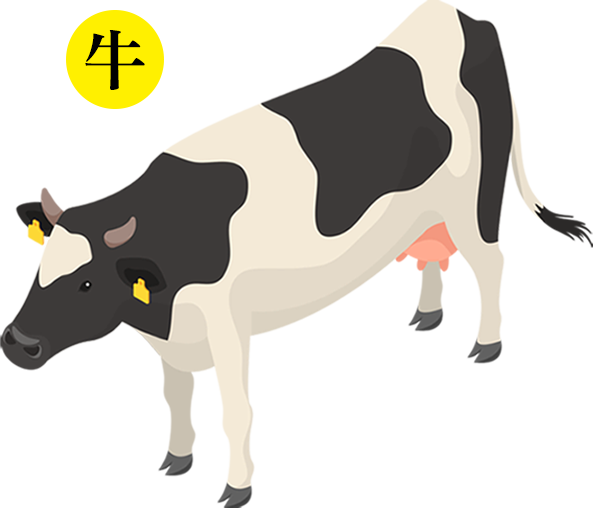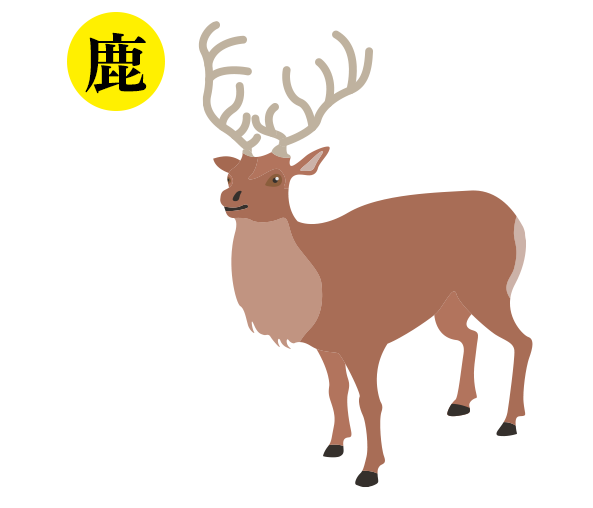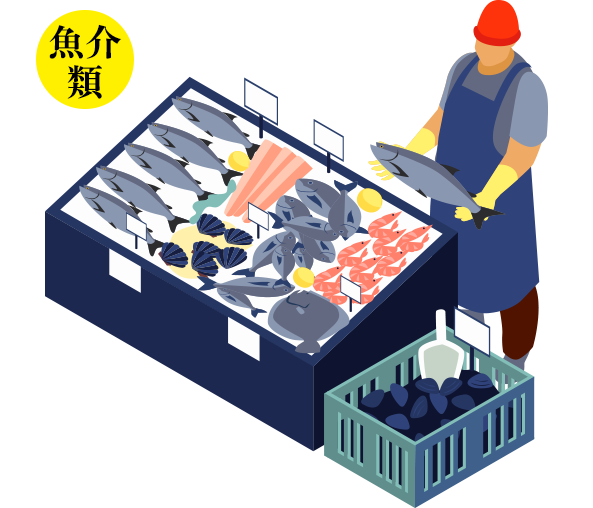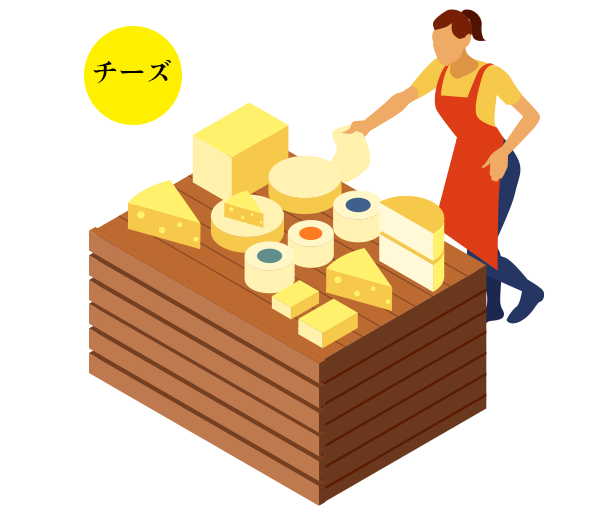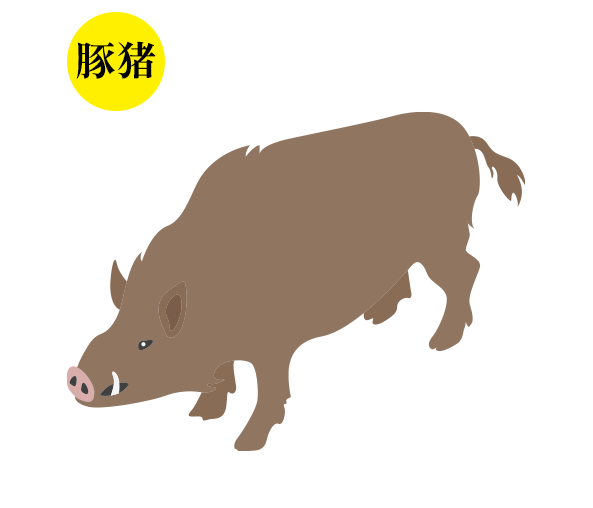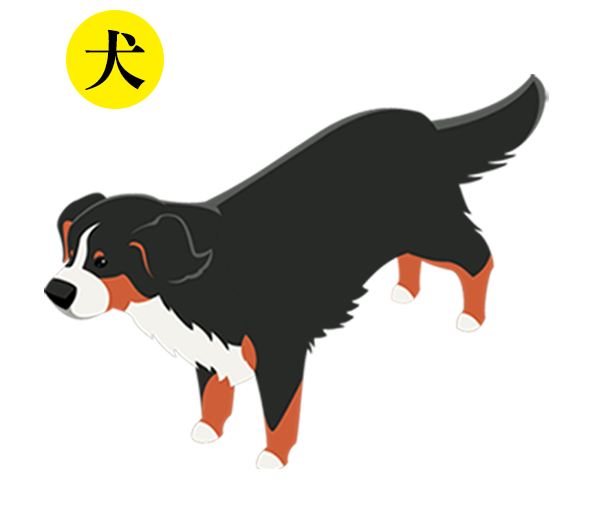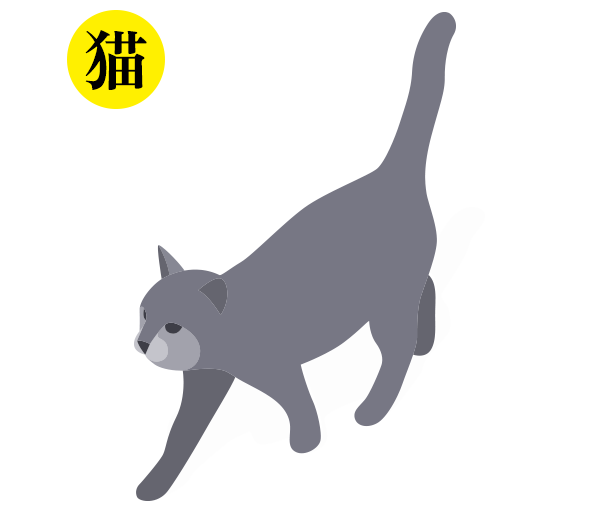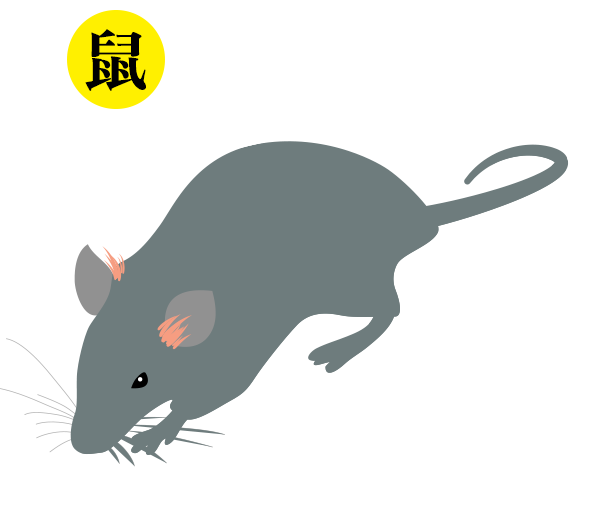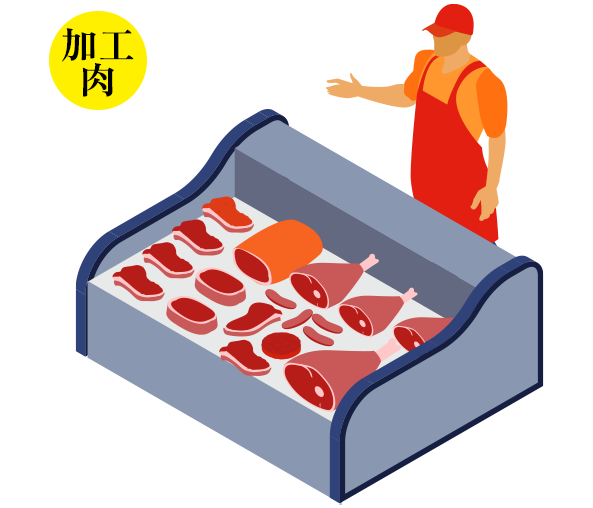肝吸虫症| Clonorchiasis
感染経路と予防
肝吸虫Clonorchis sinensis が寄生しているモツゴ、タナゴ、コイ、フナなどのコイ科の淡水魚を生食や塩漬け、加熱不十分なまま摂取することで感染する。
流行地は、韓国、中国、台湾、ベトナム北部、ロシア極東部で、日本ではかつては流行していたが、近年は海外渡航者の症例がほとんどである。コイ科の淡水魚を生食しないことが予防となる。養殖された鯉の洗いの場合は感染の可能性は比較的低い。
病態
ヒトに摂取された幼虫は胆管や胆嚢に寄生する。成虫になるまで約1ヶ月を要し、寿命は10年から20年と言われている。
無症状であることが多いが、胆管を閉塞して胆管炎を惹き起こしたり、胆管の慢性炎症を惹き起こし胆管癌の原因となる。
診断・治療
腹部超音波検査では、胆管や肝内胆管の拡張や胆管周囲のエコー輝度の上昇等がみられる。
診断は便中や胆汁から虫卵を検出することで行う。症状の有無に関わらず、便に虫卵を認めた際は治療が必要である。抗寄生虫薬であるプラジカンテルを1〜2日間内服する。また胆管炎をきたした際は、胆道ドレナージ術が必要となる。
出典
"Acta Trop . 2020 Mar;203:105309. UpToDate :Liver flukes: Clonorchis, Opisthorchis, and Metorchis. last updated:Feb 17, 2022."このサイトの執筆者一覧
植田 秀樹,大川 直紀,大塚 喜人,窪田 佳史,倉澤 勘太,津山 頌章,中尾 仁彦,藤井 元輝,松田 直也