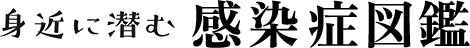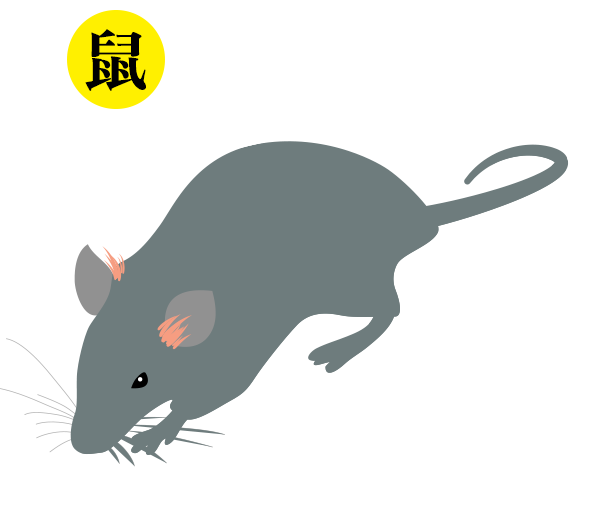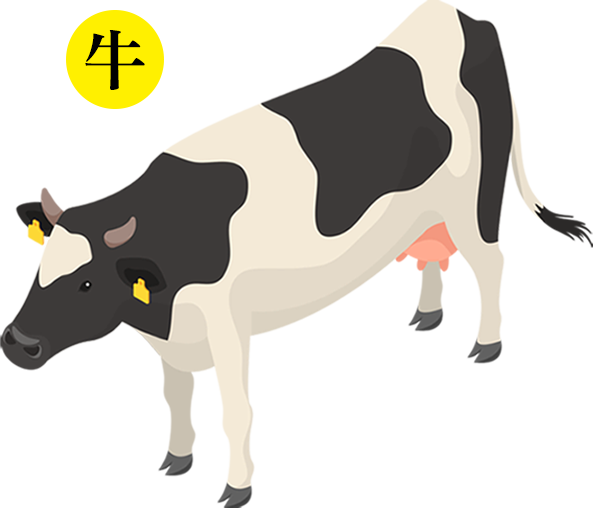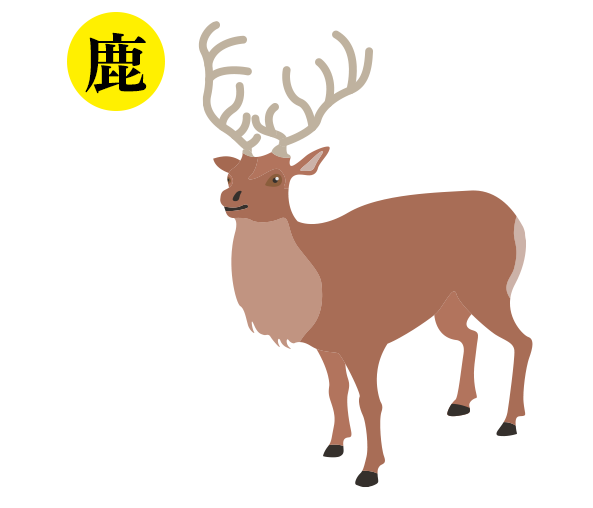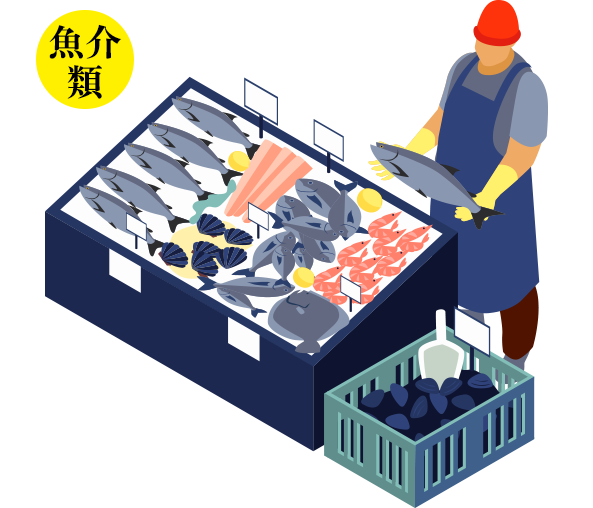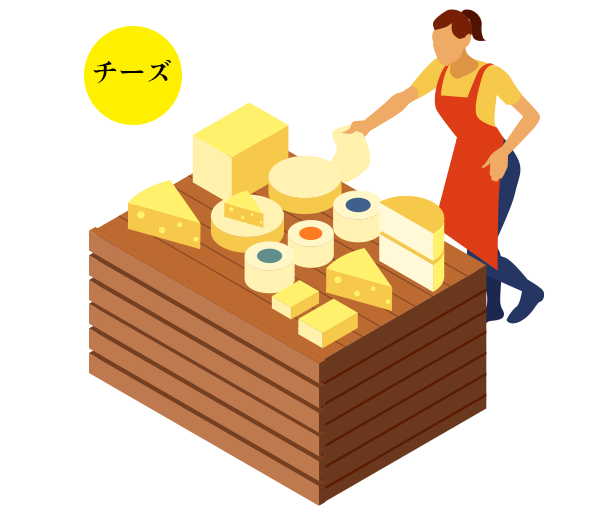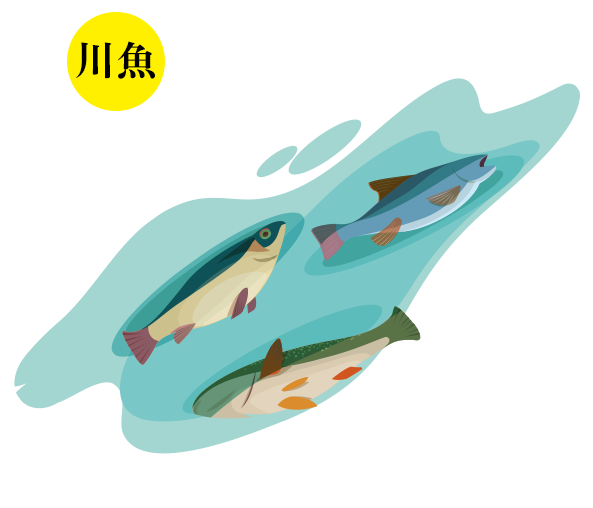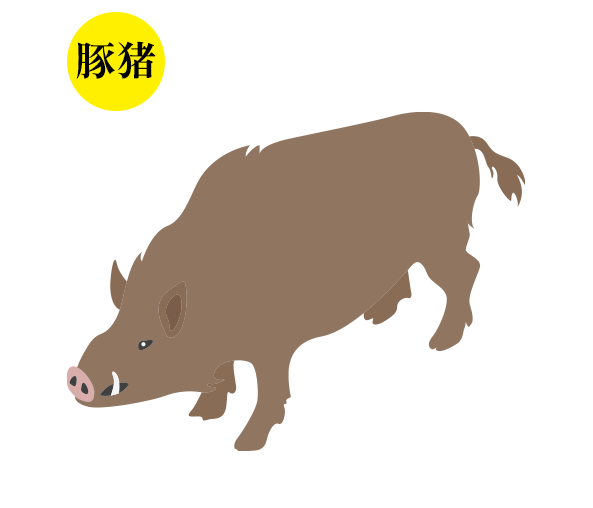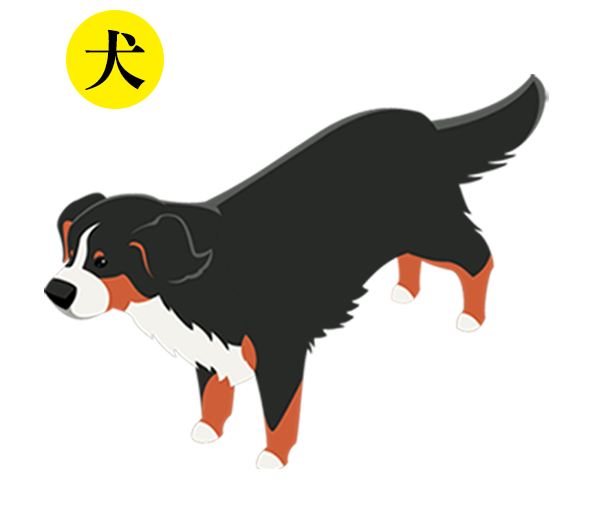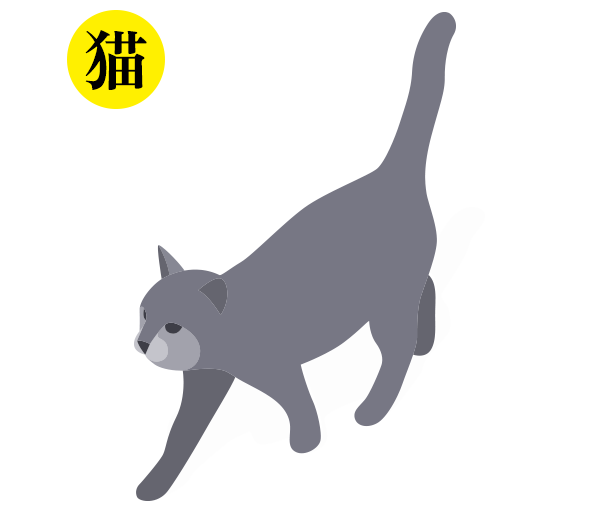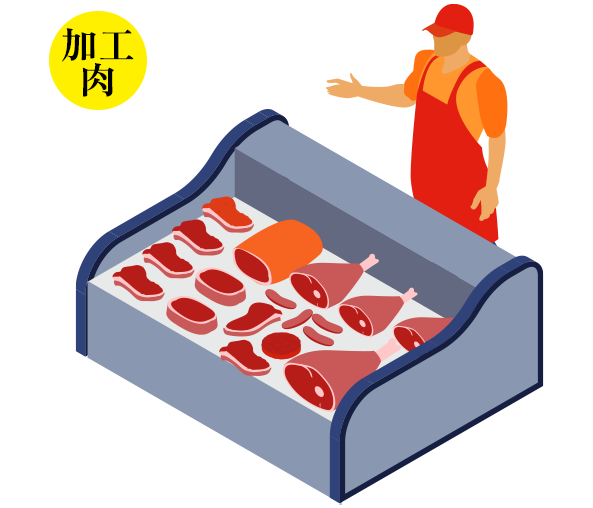レプトスピラ症| Leptospirosis
感染経路と予防
保菌動物(ネズミなど)の尿中に長期間菌が排出される。感染動物の尿や尿に汚染された水や土から皮膚や口を介して感染する。
ラフティングやトライアスロンなどで川に入ったことによる集団感染が報告されている。
予防としては沢水や川などの汚染された可能性のある水を飲まない、素足で入らないようにする。必要時には、手袋やゴーグルなど着用して、水や土壌に直接触れないようにする。
ネズミの駆除や侵入阻止等の動物対策により、建物内の清潔を保つ。感染の可能性のある動物と接触する場合は手袋やマスク等を着用する。
病態
5~14日の潜伏期の後に、38~40度の発熱、悪寒、頭痛、筋肉痛、結膜充血等の初期症状で発症する。
重症の場合は、発症後5~8日目に黄疸、出血、腎機能障害等の症状が現れワイル病と呼ばれる。
90%程度は無症状または自然に軽快する発熱のみだが、5-10%の症例が重症化する。その場合は二相性に症状が出現する。初期は急性の発熱に頭痛などを伴い、photophobiaや眼窩後部痛、悪寒戦慄、腓腹筋や腰の痛み、結膜充血を伴う。第二相は免疫フェイズと呼ばれ、不整脈、循環状態の破綻、出血、黄疸、肝不全、無菌性髄膜炎、呼吸不全、腎不全をきたす。
診断・治療
血液、髄液、尿を用いて分離培養が可能であるが、専用の培地が必要である。実臨床では血液、血清、髄液、尿からのレプトスピラ核酸検出検査と顕微鏡下凝集試験法 (Microscopic Agglutination Test: MAT)によるペア血清を用いた抗体の検出が確定診断に用いられる。
治療は軽-中等度の場合には、ドキシサイクリン、アジスロマイシン内服が使用される。重症の場合は一般的にペニシリン系抗菌薬による点滴治療が行われる。
出典
動物由来ハンドブック 2022s
https://www.kansensho.or.jp/ref/d75.html
https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2020/travel-related-infectious-diseases/leptospirosis
このサイトの執筆者一覧
植田 秀樹,大川 直紀,大塚 喜人,窪田 佳史,倉澤 勘太,津山 頌章,中尾 仁彦,藤井 元輝,松田 直也