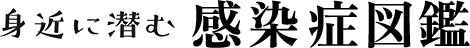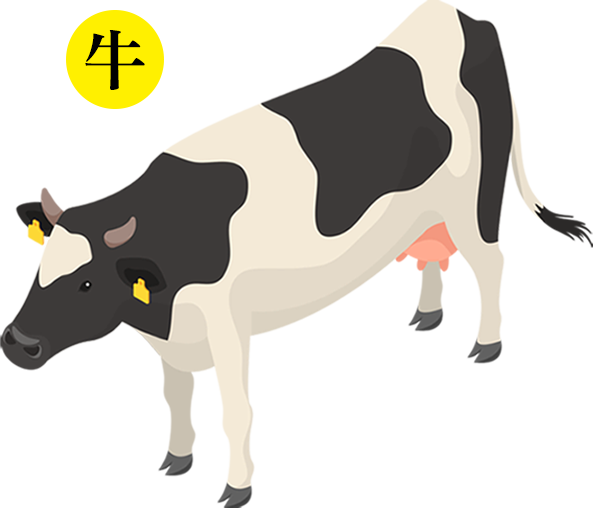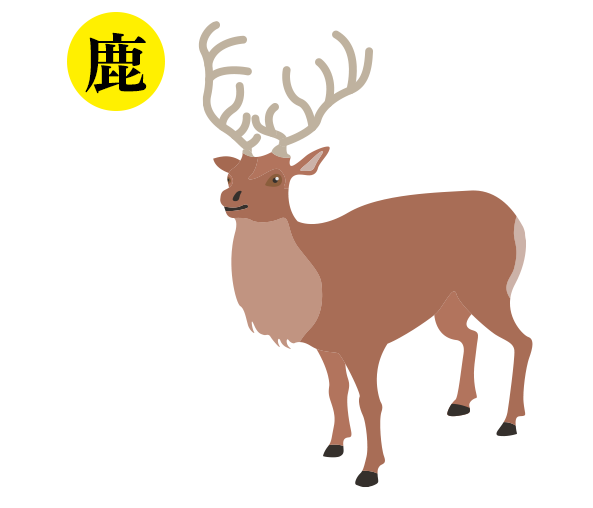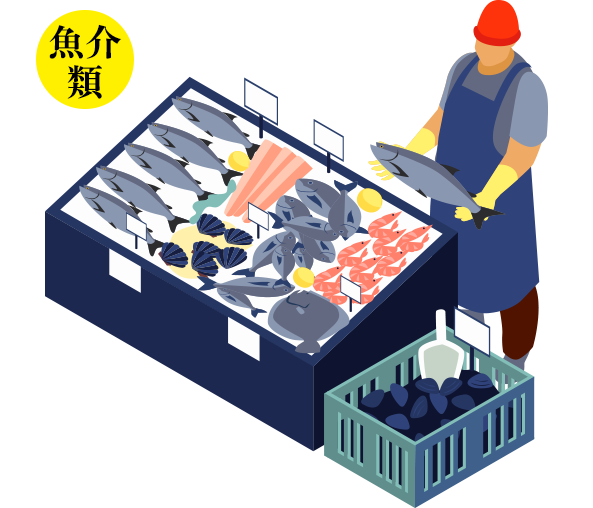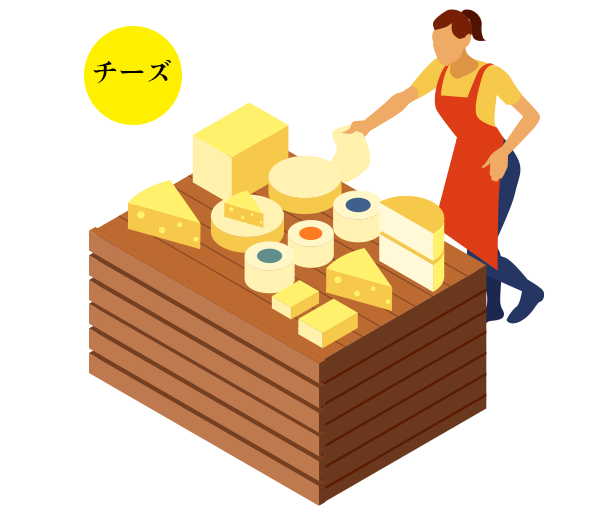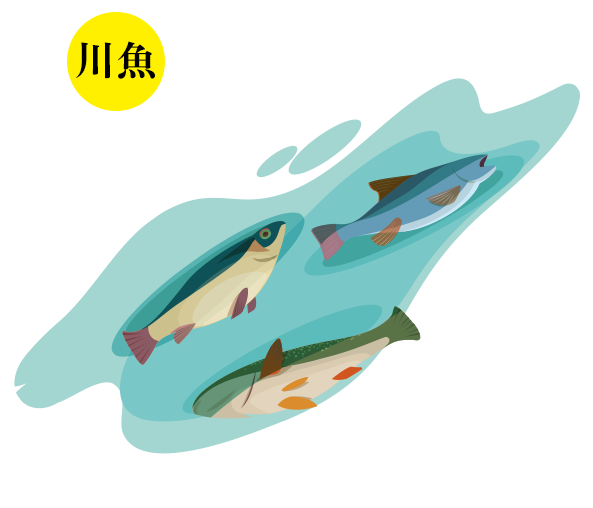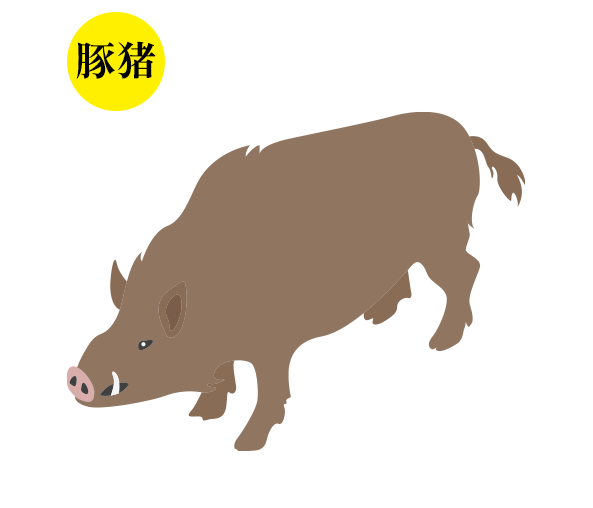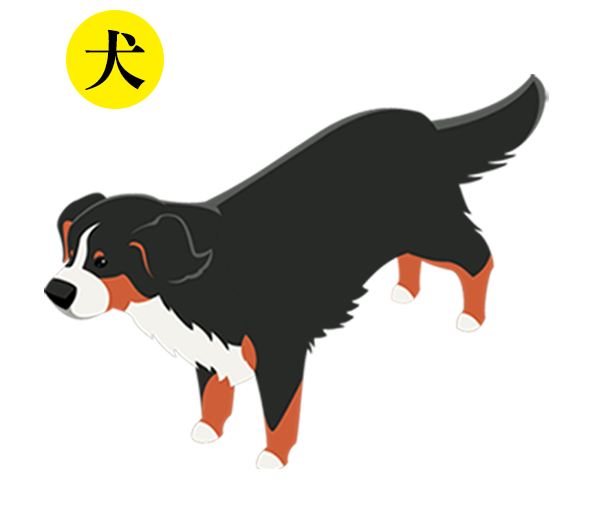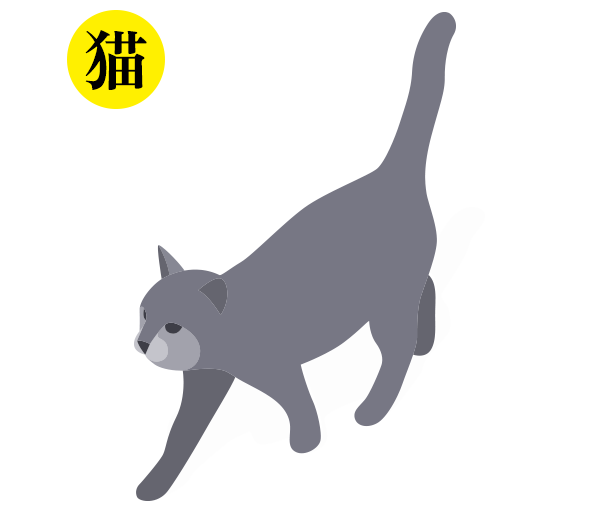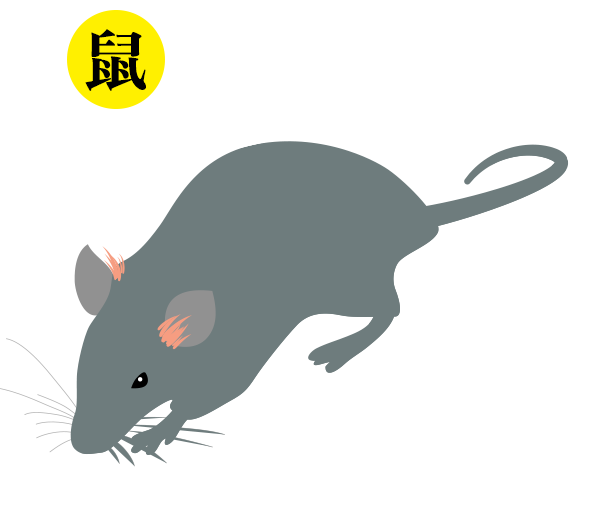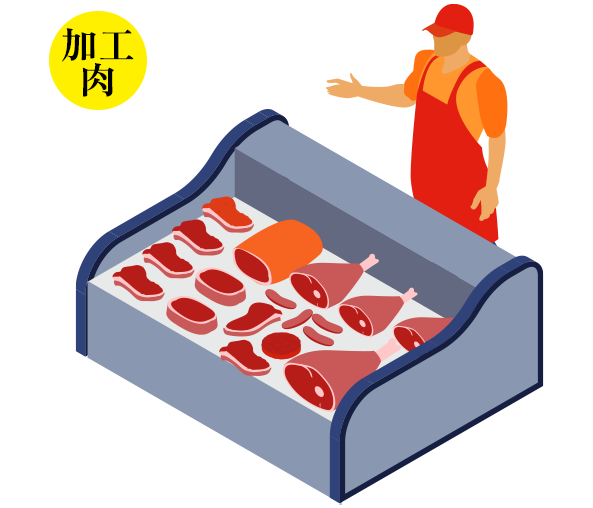腸管出血性大腸菌感染症| Enterohemorrhagic Escherichia coli infection
感染経路と予防
大腸菌(Escherichia coli)は、ヒトを含む哺乳類の腸管内に常在し、ほとんどは無害だがヒトに重篤な食中毒を惹き起こすものがある。そのうちの一つが腸管出血性大腸菌である。有名なものにO157:H7株がある。
腸管出血性大腸菌はウシをはじめとした反芻動物(ウシ、ヤギ、ヒツジなど)が保菌していることが知られていいる。腸管出血性大腸菌に汚染された食品、例えば加熱が不十分な肉料理を経口摂取することで感染する。過去に日本ではユッケによる腸管出血性大腸菌による食中毒が報告されている。また、感染した患者の家族や施設の中で患者の排泄物を介したヒトからヒトへの二次感染も問題となる。
予防対策としては、腸管出血性大腸菌は熱に弱いため、食品を「十分に加熱する」ことが重要である。また小児や高齢者といったハイリスクグループに生肉や加熱不十分な食肉を食べさせないように注意が必要である。
ヒトからヒトへの二次感染に対しては、糞口感染であることから、手洗いの徹底等により予防することができる。
病態
汚染された食物を摂取することで感染する。かいわれ大根や、キュウリによる集団発生が報告されており、肉類に限らない。
特にO157:H7株はごく少数の菌で感染が成立し、トイレのドアノブを介して感染したと考えられた症例の報告がある。ベロ毒素は赤痢菌の志賀毒素と同じものであり、激しい腹痛や下痢、出血性大腸炎を惹き起こす。
”All blood, no stool" と表現されるような血便が典型的とされる。摂取から発症するまでの期間(潜伏期間)は3〜8日とされる。ほとんどの患者は10日以内に回復するが、ごく一部の患者(特に幼児や高齢者)では、合併症として溶血性尿毒症症候群(HUS)を発症し、重症例では死亡することがある。
診断・治療
診断は、病歴で過去1週間ぐらいの食事内容を聴取することが重要である。近年、法律で生肉の提供に厳しい規制が実施されている。腹痛を伴い、特に血便を認める場合は積極的に疑って便培養を提出する。
培養提出時には”病原性大腸菌疑い”のコメントをつけ、検査時に選択培地を用いるようにする。コロニーから血清型とベロ毒素産生を確認して同定する。
治療は、海外では抗菌薬の投与はHUSの発症を増やすため禁忌とされるが、日本ではホスホマイシンが投与される。脱水を防ぐための十分な水分摂取など支持的治療が行われる。
出典
国立感染症研究所.“腸管出血性大腸菌感染症とは”https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ta/ehec.html WHO.“E. coli”
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/e-coli CDC.“E. coli infection”
https://www.cdc.gov/healthypets/diseases/ecoli.html#:~:text=The%20best%20treatment%20for%20E,of%20fluids%20to%20stay%20hydrated.
このサイトの執筆者一覧
植田 秀樹,大川 直紀,大塚 喜人,窪田 佳史,倉澤 勘太,津山 頌章,中尾 仁彦,藤井 元輝,松田 直也