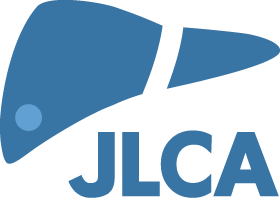1. 募集期間
| 2025年1月15日(水) |
~ |
2月26日(水)
3月5日(水)まで延長
3月12日(水)まで再延長
一般演題登録を締め切りました。
多数のご応募をいただきましてありがとうございました。 |
2. 演題登録方法
演題登録は、インターネットによるオンライン登録のみです。
演題登録画面へ進むボタンは本ページ下部にございます。
以下の注意事項を十分お読みいただいたうえで、演題登録画面にお進みください。
3. 発表形式
募集する発表形式は、次のとおりです。
| 01 |
シンポジウム(公募/一部指定) |
| 02 |
パネルディスカッション(公募/一部指定) |
| 03 |
ワークショップ(公募/一部指定) |
| 04 |
症例検討会(公募) |
| 05 |
一般演題・口演(公募) |
| 06 |
一般演題・ポスター(公募) |
※演題の採否、発表日時等は、事務局にご⼀任ください。
4. 応募資格
筆頭著者は原則として日本肝癌研究会会員に限ります。
ただし、個人会員が1名以上共同演者となっている場合は、非会員でも応募できるものとします。
<入会手続き>
「日本肝癌研究会ホームページ」よりご入会手続きをお済ませください。
5. 利益相反の開示について
本サイト内「利益相反(COI)の開示」ページをご参照のうえ、ご準備をお願いいたします。
6. 演題分類
※テーマなどは変更になる場合がございます。
シンポジウム(公募/一部指定)
| a. |
肝細胞癌薬物療法のファーストラインを考える:薬剤の選択と最適化
- 司会の言葉
- 現在、肝細胞癌に対する薬物療法のファーストラインは、複合免疫療法の適応の有無によって大別される。適応がある場合、IO+抗VEGF療法とIO+IO療法が使用可能であるが、両者を直接比較した試験は存在せず、それぞれの特性を考慮した上で治療薬を選択する必要がある。しかし、その選択には、肝細胞癌の進行度、肝予備能、抗VEGF薬や重篤なirAEへの忍容性、併存疾患、患者のADL、奏効性を優先するのか、長期予後を重視するのかといった多くの要素が複雑に絡み合うため、個々の症例に応じた最適なレジメンの決定が求められる。また、原則として複合免疫療法の適応はChild A症例に限られており、Child B症例における治療選択も依然として課題である。さらに、セカンドライン以降まで見据えた効果的なシークエンシャル治療の観点からも、ファーストラインの選択は極めて重要であるが、現時点では十分なエビデンスが確立されていない。本来であれば、biomarkerを活用した個別化治療が最も望ましいが、日常診療で実用可能なbiomarkerは未だない。そこで本セッションでは、肝細胞癌におけるファーストライン治療の選択と最適化について、多角的な視点から議論を深め、臨床現場での意思決定に資する知見を得る場としたい。
|
| b. |
Intermediate stage HCCにおけるTACEと全身薬物療法の意義
- 司会の言葉
- TACEはIntermediate HCC対する有効な治療法であるが、成績は技術に左右されるため、超選択的で効果的なTACEにより局所根治を目指す必要がある。TACEにより局所根治が困難あるいは肝機能が増悪しやすい病態がTACE不適として腫瘍数・径・形態から定義され、積極的に全身薬物療法がおこなわれつつあるが妥当性は検証が必要である。分子標的治療薬の先行投与後の計画的なTACE、あるいは複合免疫療法後のオンデマンドTACEにより臨床的完全奏効をめざす治療も広く行われつつあるが有効性と安全性の検証が必要である。
TACEによる腫瘍免疫賦活作用が免疫療法の有効性を高める可能性が議論されているが、その科学的証明が必要である。Intermediate HCCに対してTACEとVEGF阻害薬・分子標的治療薬と免疫療法を組み合わせた臨床試験も進行中であり成績が期待される。このようにIntermediate HCC に対する治療戦略は刻々と変化している。本シンポジウムでは、Intermediate HCC に対する各施設の治療戦略、成績についてご発表いただき、最適な治療戦略について討議いただきたい。
|
| c. |
肝癌微小環境に注目した新規治療法の開発~基礎と臨床から
- 司会の言葉
- 肝癌診療は、免疫チェックポイント阻害剤の導入による治療の革新と、シングルセルや空間解析技術の進展を背景に、新たな段階に入りつつある。肝癌研究においては、癌微小環境を構成する免疫細胞、線維芽細胞、血管内皮細胞などの間質細胞の機能や癌細胞を含めた細胞間相互作用を包括的に理解することが極めて重要になっている。また、癌微小環境が治療後の再発や生存率、薬物療法の効果に深く関与していることが明らかになりつつある一方で、局所治療や薬物治療が癌微小環境を変容させる可能性も示唆されている。このような知見は、肝癌診療における治療戦略のさらなる発展に向けた重要な手がかりとなる。
本シンポジウムでは、肝癌の微小環境に関する基礎および臨床研究の最新成果を共有し、癌微小環境を標的とした新規治療法の可能性を探る。また、癌微小環境と治療効果との関係やバイオマーカーについて基礎と臨床の両面から検討し、今後の課題や展望を議論する場としたい。
|
| d. |
肝癌放射線治療の新潮流:最適化された治療技術とその未来
- 司会の言葉
- 体幹部定位放射線治療や粒子線治療(陽子線治療、炭素イオン線治療)などのいわゆる根治的放射線治療が可能となり、肝癌に対する放射線治療はその重要性を増してきた。最近ではこれらの根治的放射線治療とアブレーションとの比較、またTACEとの比較を実施したランダム化比較試験の結果も公表され、放射線治療のすぐれた局所効果が認識されつつある。放射線治療の適応に関しては、ある程度コンセンサスのある病態も存在するが、さまざまな病態に応じてどのような放射線治療を選択し、どのような線量分割で実施すべきかについては必ずしも明確となっていない。また、治療中に病巣の動きをとらえて照射する新たな治療技術なども臨床応用可能となっており、今後の肝癌への応用に向けて評価が必要な領域である。
本セッションでは肝癌に対する最適化放射線治療について、標準治療との比較研究、多様な病態(肝内胆管癌を含む)への対応、新たな照射技術などについて情報共有し、今後の肝癌診療の指針とすべく公募ならびに指定演者により討論を行う。
|
| e. |
BR-HCCの課題と展望
- 司会の言葉
- 日本肝癌研究会、日本肝胆膵外科学会より2023年11月、Expert Consensus Statementとして肝細胞癌の腫瘍学的切除可能性分類が発表された。この分類により複数の診療科にまたがり共通のプラットフォームで各種治療の有用性の検証や集学的治療ストラテジーの有効性評価が検討できる状況となっている。本シンポジウムでは腫瘍学的切除可能性分類におけるBorderline resectable HCC(BR-HCC)を中心に、腫瘍・患者病態別の肝切除・局所治療(内科的治療・放射線治療)を中心としたフェーズ及び全身薬物療法をベースとしたフェーズの中での本分類の有用性や課題等を明らかにし、最終的には病態別に患者の全生存率を可能な限り伸ばすことのできる治療ストラテジーの構築に寄与できればと考えている。
本シンポジウムでは、広い診療分野よりBR-HCCに対する治療ストラテジー別の成績をご報告いただき、BR-HCCにおける集学的治療の最適解を求めつつ、同分類の今後の課題や展望を議論する場としたい。
|
パネルディスカッション(公募/一部指定)
| a. |
全身薬物療法の二次治療以降をどう考えるか?
- 司会の言葉
- 肝細胞癌の薬物療法は分子標的薬の時代から複合免疫療法の時代となり、免疫療法が奏効した症例では効果が持続し、長期生存も得られるようになってきている。しかしながら、持続した効果が得られない症例や、効果が全く得られない症例も存在し、これらの症例の後治療をどのように組み立てていくかは臨床上の重要な課題である。一方、複合免疫療法が困難な症例に対しては、一次治療として分子標的薬や免疫チェックポイント阻害剤(ICI)単剤が推奨されるが、分子標的薬治療における逐次療法の重要性が多数報告され、ICI単剤においても治療成績の向上には後治療が重要になると考えられる。
そこで、本パネルディスカッションでは、肝細胞癌薬物療法の二次治療以降における薬剤選択や治療成績についてご発表いただき、最適な治療方針について議論いただきたい。
|
| b. |
肝癌アブレーション療法の進化:ラジオ波 vs マイクロ波 そして 新技術
- 司会の言葉
- 肝癌アブレーション療法は国内外で広く実施されており、その治療手技は確立されつつある。造影超音波やフュージョンイメージの活用もますます進化している。一方で、ラジオ波(RFA)とマイクロ波(MWA)のそれぞれの適応と選択、対極板の貼付位置、焼灼や熱凝固アルゴリズムなどが標準化されておらず、施設間での差異が依然として存在する。さらに、肝細胞癌以外の肝原発悪性腫瘍や転移性肝癌に対するアブレーション療法のエビデンスは乏しく、全身薬物療法との併用による治療効果の向上も今後の課題である。また、アブレーション療法を安全かつ効果的に実施するための施設ごとのトレーニング方法の標準化も重要な課題であり、その取り組みは今後の発展に不可欠である。これら多岐にわたるテーマについて、多くの先生方からの活発な演題応募を期待するとともに、本セッションが臨床現場における治療戦略の構築に寄与することを願っている。
|
| c. |
肝癌診療をサポートするバイオマーカーの未来:臨床応用の最前線
- 司会の言葉
- 広義のバイオマーカーとは、生体内の物質や生理学的指標を指す。肝癌診療におけるバイオマーカーは、サーベイランス、診断、病態把握、治療効果や副作用の予測、治療のモニタリング、予後予測など、様々な場面での活用が期待されている。日常臨床で広く利用される血液検査、画像検査、病理組織の活用に加え、臨床検体のオミクス解析、例えばシングルセル解析による細胞レベルでのサブタイプの解明や、スペーシャル解析による腫瘍微小環境の空間的理解などの技術革新が進み、AI技術の応用も試みられている。これら最先端技術により新たな可能性が広がり、診断・治療戦略に革新をもたらす可能性を秘めている。しかし臨床導入に向けて、さらなる実証研究と標準化が不可欠である。本セッションでは、肝癌診療全般における新規バイオマーカーの探索、基礎から臨床への橋渡しを目指す研究に関する演題、また既存技術の改良や、実際の臨床現場における応用例に関する発表を広く募集する。肝癌診療におけるバイオマーカーの可能性と課題について、多角的な議論を通じ、次世代技術と臨床応用の接点を深めるとともに、肝癌診療の未来に新たな道筋を示す機会としたい。
|
| d. |
大腸癌肝転移の治療最適化:多岐にわたるアプローチ
- 司会の言葉
- 大腸癌症例において肝転移の制御は予後延長に重要な因子となる。大腸癌治療ガイドライン2024年度版では、肝転移の治療方針として、①根治切除可能な肝転移は肝切除が推奨される。②切除不能な肝転移で全身状態が保たれる場合は全身薬物療法を行う。③熱凝固療法はマイクロ波凝固療法とラジオ波凝固療法があり、選択肢のひとつとなる。と記載されている。これらガイドライン推奨治療以外には、腫瘍個数が限られている症例に対して従来から用いられてきた放射線治療の他、近年では重粒子線治療や陽子線治療が適応となっている。また、切除不能多発で全身化学療法不応症例に対してはTACEや肝動注がもちいられることもある。これら多岐にわたる治療法は、それぞれ単一でなく併用治療として行われることも少なくなく、集学的治療や個別化治療の重要性が注目されている。本セッションでは、各治療モダリティーの適応や治療成績を踏まえ、大腸癌肝転移の治療の最適化についてディスカッションしたい。
|
| e. |
TACEとHAICの今後
- 司会の言葉
- 肝細胞癌治療においては、複数の複合免疫療法およびTKIが使用可能となり、治療成績が向上している。これに伴って、従来行われてきたTACE、HAICの適応については、薬物療法の発達とともに少しずつ変化しつつある。薬物療法の適切な導入の観点からTACE不応の定義やTACE不適の概念が登場し、その適応が見直されている。生存期間延長を目指して、薬物療法にTACEやHAICなどの局所療法を組み合わせた集学的治療も行われるようになり、局所療法の役割が変化している。一方、薬物療法が不適、または不応に対する対応についてはまだまだUnmet needsであり、このような場合にはTACEやHAICなどの従来の治療方法が選択されることが多い。本セッションでは、肝細胞癌治療におけるTACEとHAICの適応や治療成績、各治療法の利点と限界、さらには全身薬物療法との併用について議論いただきたい。
|
| f. |
低侵襲肝切除の最前線
- 司会の言葉
- 近年、腹腔鏡による肝切除が一般的な技術となり、ロボット支援手術の導入も進んでいる。High-volume centerでは、十分な症例数の解析に基づいて、低侵襲肝切除の適応や手術成績を論じることができるようになった。同時に、技術面でも、trocar配置や肝離断の方法、術前シミュレーション・術中ナビゲーションの活用など、様々な工夫が採用されている。一方、各種ロボット支援装置の使い分けや若手外科医の教育が、今後の課題として認識されつつある。本セッションでは、低侵襲肝切除をさらに安全で有効な治療手段として普及させるために、各分野・各段階における「最先端」のテーマについて論じていただきたい。
|
ワークショップ(公募/一部指定)
| a. |
リアルワールドでのChild B症例に対する薬物療法
- 司会の言葉
- 薬物療法の対象として、肝癌診療ガイドラインでは「外科切除や肝移植、穿刺局所療法、TACEなどが適応とならない進行肝細胞癌で、PS良好かつ肝予備能が良好なChild-Pugh分類A症例に行うことを推奨する」と記載されている。しかし実臨床では、Child-Pugh B肝癌患者に対して投与されたケースも少なからず報告されている。従来の薬物療法は肝機能不良例では治療効果が減弱し、副作用も多いとされてきた。しかし複合免疫療法をはじめとした様々な新しい薬剤が使用されるようになり、Child-Pugh B肝癌に対する適応基準や使用時のベネフィット/リスクに対する考え方が変化してきていると思われる。本セッションでは、Child-Pugh B症例に対する薬物療法の適応基準、薬剤選択、その有効性と安全性、投与法の工夫、さらに実臨床における課題とその対応策について議論を深め、実臨床に即した最適な治療戦略を模索する機会としたい。
|
| b. |
エビデンスに基づいた肝内胆管癌に対する治療戦略―手術、薬物療法、遺伝子パネル
- 司会の言葉
- 肝内胆管癌(ICC)は肝癌の中でも発生頻度は依然少ないものの悪性度の高い腺癌であるが、 その治療戦略は近年大きな進展を遂げている。従来手術療法が根治を目指した単独の第一選択肢とされてきたが切除可能症例の限界や術後再発リスクが課題である。主腫瘍の診断のみならずリンパ節転移診断においてはルーチン検査では高い正診率が得られない。さらにリンパ節転移陽性は最も外科的予後不良因子で、外科的にリンパ節郭清の意義でのエビデンスは構築できていない。一方化学療法において2024年時点で新規薬剤や免疫療法の臨床試験結果が蓄積され、従来の標準治療に対する治療成績の改善が期待されている。また、遺伝子パネルを活用した分子標的治療が注目され、胆道癌の中でも特にICCは特定の遺伝子変異(FGFR2融合、IDH1変異など)を有する患者に高い効果を示す個別化医療の可能性が明らかになりつつある。こうした進展を踏まえ、ICCに対する手術の適応限界、薬物療法の進歩、遺伝子パネルを活用した個別化治療の可能性、組織学的悪性度の評価、粒子線治療などの治療効果などについてご発表いただき、最新エビデンスに基づく治療戦略について議論いただきたい。
|
| c. |
まれな肝がんの治療戦略:希少例に挑む
- 司会の言葉
- 細胆管癌、粘液嚢胞腺癌、肝芽腫、血管肉腫などの希少肝がんは診療経験が限られ、標準的な治療指針の確立が難しい。また肝細胞癌と肝内胆管癌両者の成分を有する混合型肝癌においても術後病理診断にて確定後、肝内再発時にはどのような治療選択を行うべきか、あるいは切除不能時のときは治療選択をどうすべきかなど、こうした症例に対し治療が奏効した例など各施設での希少肝がんに対する症例についてご報告いただきたい。
肝細胞癌においても肉腫様変化を伴う症例は希少ながらも極めて予後不良とされている。肉腫様変化は肝臓のみならず他臓器由来でも発生が報告されており、単一の臓器を対象とせず臓器横断的な治療体系を構築する必要性も考えられてきている。こうした希少な肝がんの症例の治療内容、治療経過や病理組織像の解析結果から新たな治療戦略の提案が期待されている。本セッションでは症例報告や最新の知見をご発表いただき、希少肝がんにおける診療の現状と課題について議論いただきたい。
|
| d. |
肝癌診療を担う次世代医師の獲得と育成
- 司会の言葉
- 肝癌診療は今、大きな変革期を迎えている。肝癌診療の未来を担う次世代医師の確保と育成は、極めて重要な課題である。実践的なトレーニング、臨床・基礎研究、大学院教育、人材確保といった多岐にわたる課題が山積する中、日本の肝癌診療で培われた知識や技術を次世代へ確実に継承することが求められている。同時に、次世代医師のキャリア形成を支援し、臨床および研究分野で活躍する人材を育成することは、肝癌診療の未来を左右する重要な使命である。
本ワークショップでは、肝癌診療を担う次世代医師の獲得と育成をテーマに、外科、内科、放射線科、病理などの診療科が取り組む具体的な事例を共有し、より効果的な方策を議論する。教育体制の工夫、人材確保の戦略、キャリア支援の成功例や課題を掘り下げ、実践的な取り組みや新たな試みを共有することで、より良い肝癌診療の未来を築いていくことを目指す。
|
| e. |
SLD(Steatotic Liver Disease)における肝癌マネージメントの最前線
- 司会の言葉
- Steatotic liver disease(SLD)は肝癌の主な成因である。2023年、SLDは代謝機能障害および飲酒量などによりMASLD、MetALD、ALDを含む5疾患に分類されたが、各疾患の肝発癌機序に関する基礎的な病態は未だ明らかでない。また、SLD関連肝癌の疫学、臨床的特徴、抗腫瘍薬の治療効果や予後も未だ不明である。さらに、SLDがB型肝炎ウイルス制御下やC型肝炎ウイルス駆除後の肝発癌におよぼす影響も明らかでない。患者数が増加の一途を辿っているSLD関連肝癌に対して、我々は予防や病態制御を見据えた生活習慣と節酒・禁酒指導、肥満症・糖尿病・高中性脂肪血症・高血圧症などの代謝異常に対する治療ストラテジーを包括的に検討する必要がある。本ワークショップでは、SLD関連肝癌に対するマネージメントについて各施設の取り組みについてご発表頂きたい。その上で、現在のエビデンスと問題点を共有するとともに、今後の展望について議論したい。萌芽的な研究を含め多くの施設から新規性に富む演題を期待する。
|
| f. |
バイオマーカーとしての画像診断の最新知見
- 司会の言葉
- 近年の肝癌画像診断技術の飛躍的進歩により、イメージングバイオマーカーとしての役割が確立しつつある。CT、MRI、超音波などの各モダリティにおいても、新規撮像法や解析技術の開発、人工知能の応用により、腫瘍の質的評価や病勢評価、予後予測、治療支援とシミュレーション、薬物治療モニタリングや治療効果予測が可能となり、肝癌の個別化医療の実現に貢献している。本シンポジウムでは、画像診断の可能性に焦点を当て、診断から治療までの統合的アプローチと臨床的意義について議論を深めたい。活発な意見交換を通じ、肝癌診療の新たな展望を切り開く機会となることを期待する。
|
| g. |
進行肝癌に対する薬物療法後コンバージョンのインパクト
- 司会の言葉
- 進行肝細胞癌(HCC)は、従来、化学療法抵抗性であり、薬物療法後に「コンバージョン治療」を企図することは困難とされてきたが、近年様々な分子標的薬や免疫チェックポイント阻害剤の登場により、治療戦略が大きく変化してきている。薬物療法により奏効が得られた症例でもcancer freeを企図し、コンバージョン治療を施行することが望ましいという報告がある一方で、進行HCCに対するコンバージョン治療の適応には腫瘍学的側面・技術的側面に加えて、肝機能因子の慎重な評価も求められることから、コンバージョン治療の適応判断に難渋することもある。本ワークショップでは、進行HCCに対するコンバージョン治療のタイミングと望ましい手術術式、またコンバージョン治療後の薬物療法継続の要否、レジメン選択などについて最新の知見を発表いただき、進行HCCコンバージョン治療の現時点での課題と今後の展望に関して外科、内科、放射線科、腫瘍内科の領域を問わず有意義な議論を行いたい。
|
| h. |
これからの肝癌診療における肝移植の役割
- 司会の言葉
- 肝細胞癌に対する肝移植では、背景の高発癌状態にある肝硬変を含めて治療可能であるため、長期生存が期待できる理想的な治療である。我が国では、2019年に脳死肝移植、2020年に生体肝移植の適応基準が5-5-500基準またはミラノ基準に拡大された。さらに、2024年からは脳死肝移植の登録がChild Pugh7点以上で可能となり、MELD周期加算のある肝細胞癌に対する脳死肝移植の増加が期待される。また、肝細胞癌に対する全身薬物療法をはじめとする各種治療法の進歩も加わり、肝移植が肝癌集学的治療における新たな治療選択肢として期待される。本ワークショップでは、肝移植を含めた肝癌治療の現状や肝移植後成績、現在の問題点や今後の方向性についてご発表いただき、今後の肝癌診療における肝移植の役割について議論していただきたい。
|
症例検討会(公募)
※抄録の最後に診断または治療の問題点を明示してください。
一般演題(公募)
※一般演題(公募)は口演発表とポスター発表があります。
ポスターはポスターパネルへの掲示とポスター前にて発表があります。
下記演題登録システムにて希望発表形式を選択ください。
| 01 |
画像診断 |
| 02 |
がんゲノム・バイオマーカー・リキッドバイオプシー |
| 03 |
腫瘍微小環境 |
| 04 |
肝機能評価・保持 |
| 05 |
ウイルス性肝癌 |
| 06 |
非B非C肝癌 |
| 07 |
Intermediate-stage肝癌 |
| 08 |
進行肝癌 |
| 09 |
肝内胆管癌 |
| 10 |
混合型肝癌・細胆管がん |
| 11 |
転移性肝癌 |
| 12 |
肝切除 |
| 13 |
肝移植 |
| 14 |
局所療法 |
| 15 |
血管内治療 |
| 16 |
化学療法(薬物療法) |
| 17 |
化学療法(有害事象) |
| 18 |
放射線治療(重粒子を含む) |
| 19 |
Conversion治療 |
| 20 |
併用療法(薬物療法+局所療法/放射線治療) |
| 21 |
AI/IT活用 |
| 22 |
教育・人材育成 |
7. 演題・抄録作成要綱
(1)登録可能著者数・所属機関数
- 最大著者数:筆頭著者と共著者を合わせて20名まで
- 最大所属機関数:10施設まで
(2)文字数制限
- 演題名 :日本語 全角50文字/英語 35word
- 抄録本文:全角900文字
- 総文字数:全角1,400 文字〔所属機関+著者+演題名+本文〕
※制限文字数を超えますとご登録いただけません。
※半角の英数字は、2文字で全角1文字とします。
※改行を多用すると、抄録集の印刷スペースが不足することになりますので、最小限にとどめてください。
(3)抄録本文の作成
- 抄録本文は、最初にご自身のパソコン(テキスト形式)で作成し、コピー機能を使って抄録本文用の枠内にペーストすることをお勧めします。
- 図表を挿入することはできません。
(4)入力の際の注意事項
- 英字および数字は、半角で入力してください。
- ①②③のような丸付き数字は使用できません。
- ⅠⅡⅢのようなローマ数字も使用できません。英字の組み合わせで、II、VI、XIのように入力してください。
- αβγ等を使用するときはα β γを使用してください。
- その他の特殊文字を使用される場合は、特殊文字一覧を参照してください。
- タイトルおよび抄録本文で上付き文字、下付き文字、イタリック文字、アンダーラインなどを使用する際は、書式を変更したい範囲をそれぞれ<SUP></SUP>、<SUB></SUB>、<I></I>、<U></U>で挟んでください。
- 行の途中で改行したい場合は、改行する文の冒頭に<BR>を入力してください。これらの記号はすべて半角文字を使用してください。
- 不等号「<」「>」を使用する時は、全角文字を使用してください。
(5)パスワードの設定と管理、登録の完了
- 登録した抄録を確認・修正するためのパスワード(半角英数文字6~8文字)を入力してください。
- 登録が終了しますと、「登録番号(10000番台)」が自動発行されます。登録番号の発行をもって、演題応募登録は終了です。画面に登録番号が表示されない場合は、受け付けられていませんのでご注意ください。
- 発行された「登録番号」と「パスワード」は、必ずお控えください。第三者の閲覧、悪用を防止するため、登録番号とパスワードの問い合わせには一切応じられません。
- ご登録いただいたE-mailアドレスに登録完了のメールが送信されます。届きましたら、必ず登録内容をご確認ください。
- 登録完了のメールが送られてこない場合は、ご登録のE-mailアドレスが間違っている可能性があります。確認・修正のページで正しく入力されているかお確かめください。携帯電話のアドレスには通知が届かない可能性がありますので使用しないでください。
(6)抄録内容の修正・削除
- 登録された演題の修正は、確認画面より行うことが可能です。演題登録期間内であれば、「登録番号」と「パスワード」を入力することにより、何度でも修正・確認をすることができます。また、削除することもできます。
- 修正するたびに、新規登録ボタンを使用すると、同一演題が重複登録されてしまいますのでご注意ください。
8. 演題採択通知
- 演題の採否および発表日時は、事務局にご一任ください。
- 発表形式はご希望を最大限尊重いたしますが、ご希望とは異なる発表形式となる場合がございますことをご了承ください。
- 演題の採否および発表日時は、登録のE-mailアドレス宛にお送りいたしますので、正確に入力をお願いいたします。
9. 演題登録時の注意事項
- UMINオンライン演題登録システムでご利用になれるブラウザについては、UMIN演題登録画面上部のご案内にて、最新の情報をご確認ください。ご案内のブラウザ以外はご利用にならないようお願いいたします。各ブラウザは、最新バージョンの使用を前提としています。
- オンライン演題登録システムについてご不明な点は、まずUMINオンライン演題登録システムFAQをご覧ください。
- 暗号通信のご利用をお勧めいたします。平文通信では、情報の通り道でデータの盗聴や改ざんの可能性があります。一方、暗号通信ではデータが暗号化されているため、安全に送受信が可能です。平文通信は、施設やプロバイダーなどの設定や環境に問題があり、暗号通信が使えない場合に限ってご利用ください。
- 締め切り直前はアクセスが集中し、回線が混雑することにより演題登録に支障をきたすことも予想されますので、余裕を持ってご応募いただくことをお奨めいたします。
- 演題の登録に関するお問い合わせは、本ページ下部にございます運営事務局までお問合せください。
10. 演題登録画面
下記のボタンより、演題登録画面にお進みください。
暗号通信(推奨)
平文通信
11. 倫理問題
発表内容は、倫理上問題になることがないように配慮をお願いします。
※倫理指針につきましては、下記を参照してください。
- 「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」
(文部科学省/厚生労働省/経済産業省)
- 「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス」
(文部科学省/厚生労働省/経済産業省)
12. 演題登録に関するお問い合わせ先
第61回日本肝癌研究会 運営事務局
株式会社コンベンションリンケージ内
〒531-0072 大阪市北区豊崎3-19-3 PIAS TOWER 11F
TEL:06-6377-2188 / FAX:06-6377-2075
E-mail:jlca61@c-linkage.co.jp